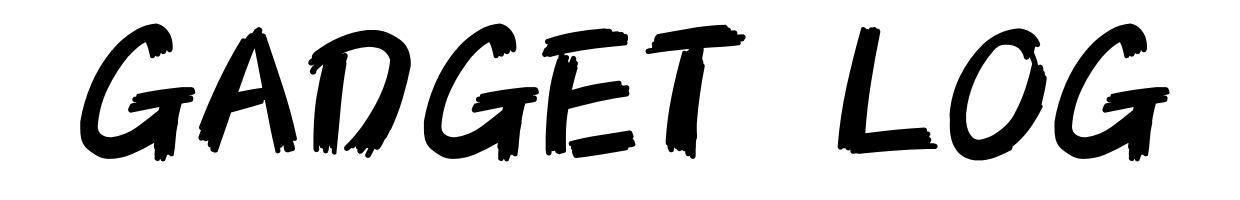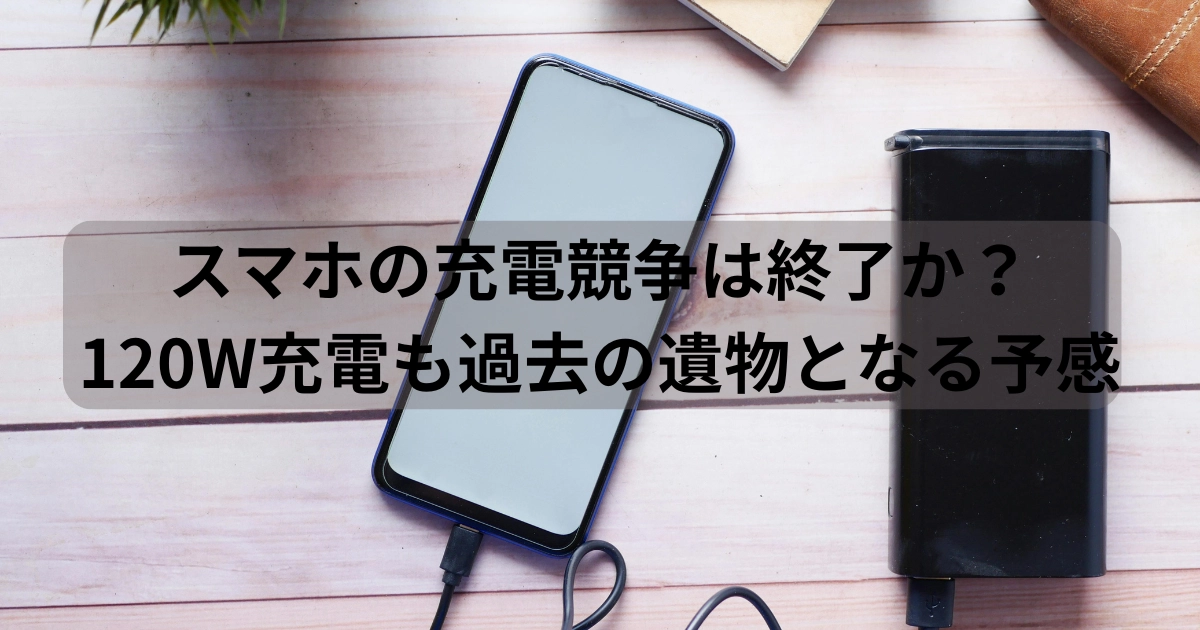2025年に発売が発表されたiPhone17ですが、日本版ではeSIMのみの対応となり物理SIMは差し込めない仕様となり話題となりました。
まだまだ物理SIMを使用する人が多い日本市場ですが、eSIMのデメリットなども気になるところ。特に機種変更や万が一の故障のときなど、差し替えられないデメリットがどの程度あるのかは知っておきたいですよね。
この記事ではeSIMの意外と知られていないデメリットについて紹介します。
eSIMのデメリットとは?
端末が故障したら詰む

まずeSIMの一番のデメリットを上げますが、一番怖いのがスマートフォン本体が故障したときの対処です。
スマートフォンを長く使用しているとどうしても本体が故障するリスクというものがありますが、物理SIMの場合は故障しても本体からSIMカードを取り出せば終わりで、こちらを新しい端末に差し込むだけで対応は終わりとなります。
ただ、eSIMだとプロファイルが本体に入っているため、故障してしまうとSIMカードを取り出すというのが不可能となり、再発行の手続きをキャリアで行う必要があります。
また、再発行にも時間を要する場合がありますし、SMS認証などを行っているサービスがある場合、手間が掛かってしまうのも結構困るところですね。
対応しているモデルが意外と少ない
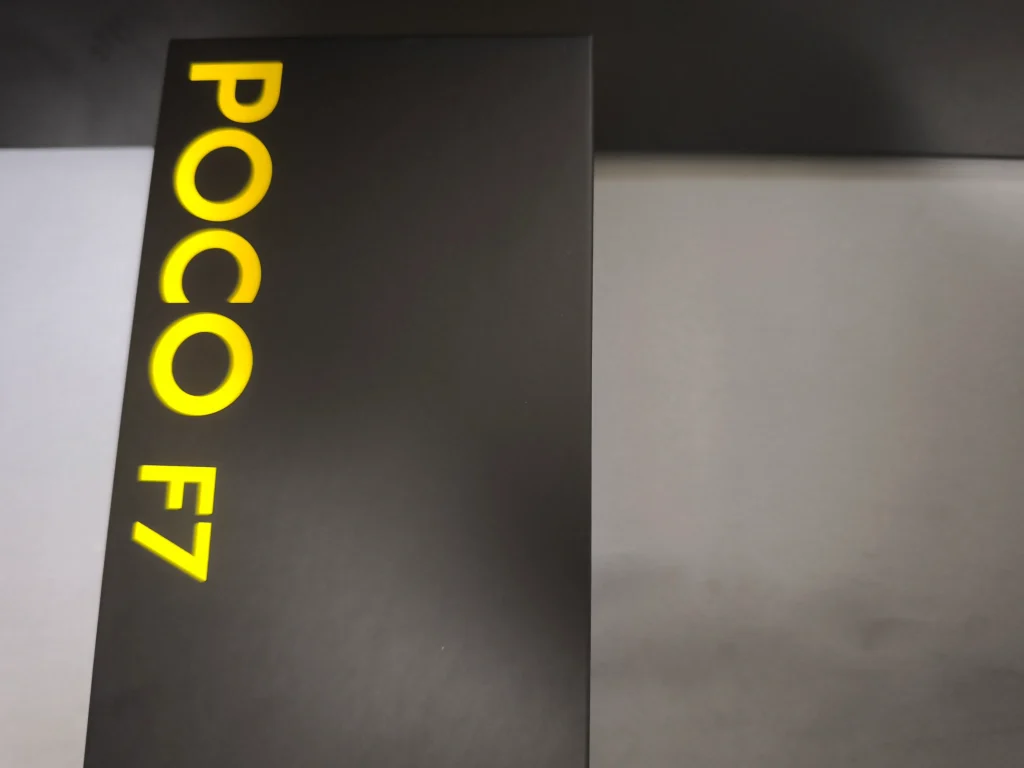
eSIMについてのもう一つのデメリットですが、対応しているモデルが意外と少ないところで、Androidでは格安モデルを中心に物理SIMのみというモデルが存在します。
つまり乗り換えなどでも選択肢が限られてしまうというところで、eSIMを使った状態でeSIM非対応の機種には乗り換えできず、物理SIMを発行するとなると大抵は手数料が発生してしまうことになりますね。
iPhone17ではeSIMのみとなりましたが、今後Androidスマホがこの流れに乗るかというのも注目ポイントだと思います。
格安SIMは非対応というケースも
最後に挙げるデメリットとしては一部の格安SIMでは物理SIMのみというパターンもあり、この場合だとeSIMのみ対応のモデルを使っていると乗り換えできない点です。
特にiPhoneは本体も高額ですし、通信料金を抑えたくて格安SIMを使いたい人も出てくるかもしれませんが、eSIMのみのモデルを使っていると乗り換えに関しても選択肢が減るという点が注意です。
利用の動向などを見てeSIM対応になる可能性はあるものの、技術的にはすぐに対応するというのが難しい点があるのも事実です。
結論:サブ回線としてならおすすめ
結論を言うとeSIMは便利なものの一定のデメリットがあるのも事実で、特に初心者などは使い方には注意する必要があり、故障などでも対応に難儀するという点が要注意となります。
個人的にはサブ回線としてeSIMを使うのは便利で、特に海外旅行などで現地のSIMを購入するときにeSIMを選択すると、面倒な作業なども必要ないですしオススメかなと思います。
参考になれば幸いです。それでは。